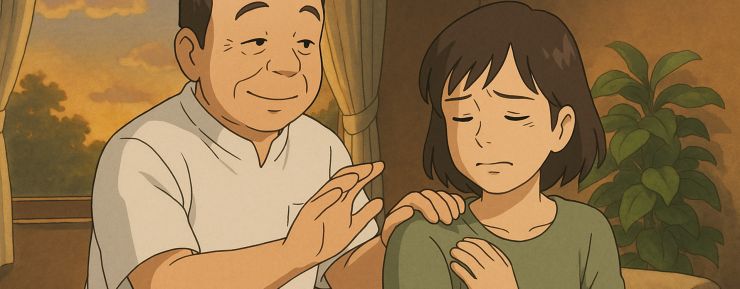秋のだるさ・冷えの原因を知ろう
秋になると、日中と朝晩の気温差が大きくなり、体温調整の負担が増えます。また、夏の疲れや暑さで乱れた生活リズムが影響し、体の回復力が落ちやすくなります。具体的な原因は次の通りです。
- 血流の低下:気温が下がると血管が収縮し、手足や腰回りの血流が滞りやすくなります。血流が悪くなると、酸素や栄養の供給が滞り、体が重くだるく感じます。
- 自律神経の乱れ:日照時間の短さや気温差により、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズにいかなくなります。結果として、寝つきが悪くなったり、起床時の疲労感が増します。
- 体内リズムのズレ:夏の暑さで寝不足になったり、生活時間が不規則になると、体内時計が狂いやすくなります。これが秋になっても残ると、だるさや冷えの原因になります。
- 栄養バランスの乱れ:夏の食生活が偏っていた場合、体の回復に必要なビタミンやミネラルが不足していることがあります。特に血流や体温維持に関わる鉄分やマグネシウム、ビタミンB群が不足すると、疲れや冷えを感じやすくなります。
気功で全身を巡らせるメリット
気功は、呼吸・意識・体の動きを組み合わせて、体内の“気の流れ”を整える伝統的な健康法です。特に秋のだるさや冷えに対しては、次のようなメリットがあります。
- 血流やリンパの循環が改善され、手足や腰回りの冷えを軽減できる
- 自律神経のバランスを整え、睡眠や目覚めの質が向上する
- 体全体が温かくなる感覚を得られ、日中の活力がアップする
- 簡単な動作や呼吸法を毎日取り入れるだけで、無理なく習慣化できる
1日5分でできる全身ポカポカ気功
忙しい方でも続けやすい、短時間で効果を感じやすい気功法をご紹介します。朝や夕方の習慣に取り入れると、体が温まり、だるさを感じにくくなります。
1. 深呼吸で体内を温める(2〜3分)
まずは呼吸に意識を向けます。背筋をまっすぐにして立つか座り、鼻からゆっくり息を吸い、口から長く吐きます。吸う息で新鮮な気が体に入るイメージ、吐く息でだるさや冷えが外に出るイメージを持つと効果的です。
ポイント:
- 呼吸は「吸う:吐く=1:2」のリズムを意識すると自律神経が整いやすい
- 肩や首の力を抜き、リラックスした状態で行う
2. 手足のゆっくり回し(3〜5分)
血流を促す簡単な動作です。肩や腕を大きく回し、手首・足首・膝・腰をゆっくりひねります。ポイントは「力を抜く」「呼吸と連動する」ことです。血液やリンパの循環が改善され、体全体が温かく感じられます。
- 肩回し:前後各5回、呼吸に合わせてゆっくり動かす
- 手首・足首回し:各5回、足は座った状態でも可能
- 腰ひねり:両手を腰に置き、左右にゆっくりひねる(3〜5回)
3. 気のボールイメージ(1〜2分)
両手を胸の前で軽く丸め、手の間に気のボールを作るイメージをします。息を吸うとボールに気が集まり、吐く息で体全体に流れるイメージを繰り返します。体がポカポカと温かくなる感覚を意識すると血流改善につながります。
応用:
- 疲れが強い部分に手を置き、気を送るイメージで重点ケア
- 呼吸と同時に軽く手足を伸ばすと、より全身の巡りが改善される
日常生活で意識したいポイント
気功だけでなく、生活習慣も整えることで効果が高まります。
- 温かい飲み物やスープで内側から体を温める
- 朝や昼に軽い運動やストレッチを取り入れ、血流を促す
- 寝る前にスマホを控え、睡眠環境を整える
- 長時間同じ姿勢を避け、こまめに体を動かす
- 栄養バランスを意識し、鉄分やビタミンB群、マグネシウムを補給する
季節ごとの工夫でさらに効果UP
秋の寒暖差に合わせて、日中は軽く羽織れる服装を選び、夜は暖かくして眠ることも大切です。また、窓を開けて新鮮な空気を取り入れることで、体内の循環を助けることができます。
簡単な秋バテ予防ポイント:
- 朝の光を浴びて体内時計をリセットする
- 温かい朝食で体温を上げ、血流を促進
- 週に1〜2回、軽い有酸素運動で全身の巡りを改善する
まとめ
秋は体がだるく感じやすい季節ですが、気功を取り入れた深呼吸・手足のゆっくり回